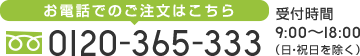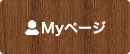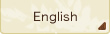ローヤルゼリーとローマ法王
養蜂によって得られるハチミツやローヤルゼリーは、
健康食品としてだけでなく、化粧品などの美容分野でも
多角的に応用されるようになっています。
ミツバチとの関わりの歴史は大変古く、
紀元前6000年ごろの人間の住居跡として有名な、
スペイン東部のラ・アラーニャ洞窟の内部に描かれたの壁画に、
ミツバチが飛んでいる様子とハチミツを採る人が描かれていることからも伺えます。
古代ギリシアの哲学者のアリストテレスは、
彼の著書である「動物誌」の中で、ローヤルゼリーを
ハチミツとは違う『濃厚な蜂蜜に似た淡黄色の柔らかいもの』と表現し、
それが固まると女王蜂になると考えていました。
実際には、
その柔らかいものとして書かれていた
ローヤルゼリーの固まりの中に産み付けられた卵が孵化し、
ローヤルゼリーを食べて女王蜂になります。
その淡黄色の固まりが「ローヤルゼリー」と呼ばれるようになったのは、
今から200年ほど前に、フランソワ・ユベールが「蜜蜂の新観察」の中で、
「ゼリー・ロワイヤル」と記したのが最初だと言われています。
その後、1950年代になるとフランスでは、
ローヤルゼリーが保健省の認可を得て、
病院で薬品として処方され始めます。
ちょうどそのころ、ローマ・カトリック教会の頂点に立つ
ローマ法王(ピオ12世)が危篤状態に陥いりますが、
主治医の判断でローヤルゼリーを投与したところ、
病状が完全に改善しました。
この奇跡的な回復劇は、ドイツの国際学会で発表され、
さらに1958年にローマで開催された国際養蜂会議でローマ法王自ら、
「私はローヤルゼリーのおかげで命が救われた」と演説します。
この出来事は、ローヤルゼリーが世界に広く知られるキッカケになりました。
やまだ農園本舗のローヤルゼリーDX90000やロイヤルプロポリススーパー5000DXにも
健康・美容成分を含む女王蜂の特別食が高配合されています。